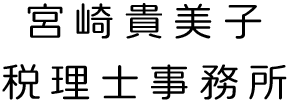重加算税は、通則法第68条第1項又は第2項に規定する「国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装した」事実がある場合に賦課され、具体的には事務運営指針に明記されています。
「隠蔽し、又は仮装し」とは、事務運営指針に明記されているとおりです。
① いわゆる二重帳簿を作成していること。
② 帳簿、原始記録、証ひょう書類、貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳明細書、棚卸表その他決算に関係のある書類を、破棄又は隠匿していること。
③ 帳簿書類の改ざん(偽造及び変造を含む。以下同じ。)、帳簿書類への虚偽記載、相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成、帳簿書類の意図的な集計違算その他の方法により仮装の経理を行っていること。
④ 帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず、売上げその他の収入(営業外の収入を含む。)の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること。
⑤ 特定の損金算入又は税額控除の要件とされる証明書その他の書類を改ざんし、又は虚偽の申請に基づき当該書類の交付を受けていること。
⑥ 簿外資産(確定した決算の基礎となった帳簿の資産勘定に計上されていない資産をいう。)に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと。
⑦ 簿外資金(確定した決算の基礎となった帳簿に計上していない収入金又は当該帳簿に費用を過大若しくは架空に計上することにより当該帳簿から除外した資金をいう。)をもって役員賞与その他の費用を支出していること。
では、所得金額の全部又は一部を申告しない不申告行為やつまみ申告が重加算税の賦課要件である隠ぺい又は仮装行為にあたるのでしょうか?
過少申告については、平成7年4月28日最高裁第二小法廷判決において、「重加算税を課するためには、重加算税制度の趣旨にかんがみれば、架空名義の利用や資料の隠匿等の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく、納税者が、当初から所得を過少に申告することを意図し、その意図を外部からも覗い得る特段の行動をした上、その意図に基づく過少申告をした場合には、重加算税の賦課要件が満たされると解すべきである」の考え方が示されました。
ここでいう「特段の行動」とは
意図的若しくはあえて無記帳、記帳操作等、申告書添付書類への虚偽記載、仮名・借名取引、仮装取引及び税務調査時の虚偽答弁等や税理士に対すると秘匿等をいいます。
今回取り上げるのは医療機関に対する技師派遣事業による所得を意図的に除外して確定申告を行い、同様にその事業の存在を隠蔽したまま消費税等の申告を行っていなかった判例(※)です。
原告は「真実の所得等を秘匿し、それが課税の対象となることを回避する意思」はなく、しかも、「積極的な所得等の秘匿工作及びそれと同視し得る不作為」も行っていないとの主張に対し、裁判所は、「真実の所得を隠蔽し、それが課税対象となることを回避するため、所得金額を殊更に過少に記載した内容虚偽の確定申告書を税務署長に提出する行為は『偽りその他不正の行為』に当たる」とし、所得税の過少申告が消費税等との関係における資産の譲渡等の秘匿工作に当たり、原告の行為が資産の譲渡等の秘匿工作を伴う不申告といえる」と認定し、「偽りその他不正の行為」に該当すると判断しました。
また、原告の「事業について納税の方法を理解していなかったから、本件事業に係る所得税及び消費税等について申告、納付をしていなかっただけである」、「事業について、法人でなければ申告できないと誤解していた」との主張についても、裁判所は、社会人として当然有すべき基本的知識の欠如を装った不合理な弁解として退けています。
このように、課税逃れの意図とそれを裏付ける行為が認定されれば「偽りその他不正の行為」に該当し、重加算税の適用対象となる。また、これに該当すれば、通則法70条4項により除斥期間は7年となるため、当該賦課決定処分も適法とされることになります。
本件は、意図的な所得隠しが消費税等にも波及することを示し、重加算税の根拠となる「偽りその他不正の行為」の解釈において重要な示唆を与えるものだと考えます。
「決算書の数字に見える人格」は過少申告行為、不申告行為にも表れます。
仮装や隠蔽の事実がなくても、『適正な申告をしない』明確な意図が認定され、その意図に基づく行為であれば、厳しいペナルティが科せられるのは公平性の観点から当然であり、いかなる主張も認められないといえます。