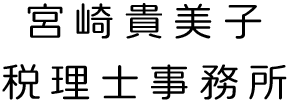― 雑所得と判断された有価証券先物取引―
決算書の数字は人の価値観の集合体です。
納税者は「これでよい」と思って申告をします。
税務署は事実を確認し、誤りを正します。
裁判所は法律と証拠に基づいて判断します。
判例を読むと、納税者の価値観がどのように主張として表れ、なぜ認められなかったのかがわかります。
判例は納税者の心理に沿って租税法を学ぶことができる、最良のテキストです。
本稿では、有価証券先物取引による所得が事業所得に該当するか、それとも雑所得と判断されるのかが争われた判例平成21年2月17日岡山地裁判決)を取り上げ、租税心理の観点から解説します。
【事案の概要】
原告は、有価証券先物取引による所得は事業所得であるから、その損失は不動産所得等と損益通算されるべきであるとして更正の請求をした
課税庁は、所得は事業所得とは認められないとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたため、それらの取消を求めた
≪事実≫
・原告は、A株式会社の代表取締役、Bの理事長、他3社の取締役や代表取締役であり、これらAグループを統括する立場にあり、不動産賃貸を業とする者である
・原告は、先物取引による所得について事業所得として申告しておらず、先物取引による利益が出た平成11年度分は雑所得として申告していた
≪取引状況≫
・平成12年 984回、423億5136万円
・平成13年 2265回、947億6760万円
・平成14年 2067回、704億4336万円
【課税庁が把握した事実】
・原告は、主として給与収入及び不動産賃貸収入を生活の資としており、Aグループにおいて雇用した従業員にその職務の傍らで先物取引に係る雑務的な手伝いをさせ、それ以外に同取引に精通した専門家や同取引を行うための従業員を雇用してはいない
・先物取引を行うに当たり、BやA等の事務機器及び事務所を使用しているが、その使用料を負担してはいない
・有価証券先物取引は、投機性が極めて強く、相当程度の期間継続して安定した利益
を上げうる可能性も極めて低い。そうすると、原告の行った本件先物取引は、原告個人の投機的な利殖活動が証券会社の大口顧客として大規模に行われたというにすぎず、社会通念上、事業であると認められるだけの形態及び実質を備えているということはできない
【納税者(原告)の主張】
・取引専用のディーリングルームを設置し、常時アシスタントを使用して多数回に
わたって多額の取引をしていることは、これが事業であることにほかならない
・当初は、証券管理部として看板を設置していたが、有価証券取引は原告個人が行っていることから、看板は撤去した
・Aグループを統括すべき地位にあり、Aグループ内における業務・勤務を行っているが、1日の大半の時間は主として先物取引を行っている
【裁判所の判断】
原告がいかに長時間を本件先物取引に費していようとも、その人的、物的設備はAグループに負っているのであって、このような面からみると、原告の先物取引が余技・余業的色彩が強いことは否めない
したがって、先物取引による所得が事業所得であり、その損失を損益通算できるということはできない
【一言】
本件では、税務調査により必要経費の計上が否認された後、先物取引を事業所得と位置づける主張がなされた点に、本件の租税心理が表れています。
税負担の結果が先に意識され、その後に所得区分の位置づけが再構成されたと見ることもできるでしょう。
所得区分は、本人の意識によって決まるものではなく、申告時点の実態が証拠となることを本件は教えています。