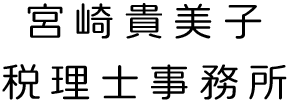税務調査における立証責任が原則として国税側にあると言われるのは、「所得の存在及びその金額について決定庁が立証責任を負うことはいうまでもないところである(最高裁昭和38年3月3日判決)」からきています。
しかしながら、支払いに関して損金算入できるか否かの立証責任は、納税者の側にあるという考え方があります。
それは、次の判例から導き出されたものです。
「一般に必要経費の点も含め課税所得の存在については課税庁に立証責任があると解されるが、必要経費の存在を主張、立証することが納税者にとつて有利かつ容易であることに鑑み、通常の経費についてはともかくとして、利息のような特別の経費については、その不存在につき事実上の推定が働くものというべく、その存在を主張する納税者は右推定を破る程度の立証を要するものといわなければならない(大阪地裁昭和46年4月26日判決)」。
つまり、税務調査において立証責任は国税側にあることが原則となるわけですが、納税者にとって立証が容易であり、それが納税者にとってその存在が有利になるような経費については、納税者に積極的に主張立証することが求められているということです。
もちろん、立証できた経費は認められることになりますが、記帳に基づいて正しい申告をする青色申告制度の観点からすると、なぜ、簿外経費が発生したのかの説明は求めらます。
領収書を紛失してしまったり、電子マネーを使用したため領収書を発行しなかったなどのうっかりミス程度のもの以外、そもそも簿外経費を主張する納税者は、正しい申告をしていないと想像できます。
では、簿外経費を主張した判例を紹介します。
契約書の相手先と代金の支払先が異なるコンサルタント料の支払について更正処分及び重加算税が課されました。
原告の帳簿書類に記載のあるコンサルタント業務契約と、締結日、場所、役務の内容及び対価において同一で、異なるのは相手方のみであり、使途も明確であるから、架空のものではないという主張に対して、必要経費として支出金額、支払年月日、支払先、支払内容等を踏まえた業務との関連性について立証されていないから、本件各事業年度における原告の所得の金額の計算上、本件各金員を「完成工事原価その他これに準ずる原価」や「当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用」に該当するものとして損金の額に算入することはできないと判断されました(令和3年12月23日東京地裁判決(税務訴訟資料 第271号‐148(順号13650))。
青色申告では、帳簿を備え付けて取引を具体的に記録することが義務付けられているので、必要経費として支出した金額、支払年月日、支払先及び支払 内容等に加え、業務との関連性についても具体的に主張立証しない限り、必要経費は 事実上存在しないものと推定されます。
また、令和4年の税制改正において、法人の隠蔽仮装行為がある事業年度において主張する簿外経費の存在が、帳簿書類等から明らかでなく、反面調査等によってもその簿外経費の起因となる取引が行われたと認められない場合には、その簿外経費の額を損金の額に算入しないこととされました。
売上に対してその経費が必要であり、実際に支出した事実が申述や証拠から立証されたとしても、「誰に渡したか」が不明の場合「使途不明金」として取り扱われる場合もあります。
「誰か」はそのもらったお金を正しく申告しているとは思えません。
課税の公平の観点から、裁判所では不正に税金の負担を逃れようとする悪質な納税者を作らないように判断され、必要に応じて法律や通達が整備されます。