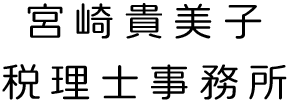副業は雑所得として申告をするような計算表が国税庁HPにありますが、そもそも事業所得で申告するのでは?と疑問に思った人もいるのではないでしょうか?
雑所得となる業務に係るもの、つまり副業に係る所得は、「総収入金額 – 必要経費」で計算され、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをいいます。
「営利を目的とした継続的なもの」はどちらにも使われている言葉ですが、事業所得と雑所得の大きな違いはなんでしょうか?
その答えは、他の所得と損益通算できるかどうかです。
赤字の所得を黒字の所得と合算して計算できれば、当然、納税額は少なくなります。
そこで、事業所得か雑所得に該当するかが問題となります。
事業所得か雑所得かで争われた判例(令和3年11月17日東京高裁判決 税務訴訟資料 第271号-129(順号13631))から、違いをみていきたいと思います。
【事案の概要】
納税者が、医療法人社団に医師として勤務して得た給与所得から、洋画等の制作及び販売から生じた所得(損失)控除し申告したところ、洋画等の制作及び販売から生じた所得は、事業所得に該当せず雑所得に該当するため、損失を給与所得から控除することはできないと判断した。
【事業所得とは】
営利性・有償性の 有無、継続性・反復性の有無のほか、自己の危険と計算による企画遂行性の有無、当該経済的行為に費やした精神的・肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、資金の調達方法、その者の職業、経歴、社会的地位及び生活状況等に加えて、事業所得の性質に照らし、「相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性」を重要な考慮要素とする。
これらを総合考慮し、社会通念に照らし、社会的客観性をもって事業と認められる実態を有するか否かによって判断される。
【雑所得と判断された理由】
制作販売等に係る売上げはわずかな額で、収益が全く上がっておらず、毎年1,000万円を超える赤字を計上していることからすれば、社会的客観性をもって事業と認められる実態を有していない。
【まとめ】
所得税法が所得を10種類に分類しているのは、その性質や発生の態様によって担税力が異なるという前提に立って、公平負担の観点から、各種の所得について、それぞれの担税力に応じた計算方法を定め、また、それぞれの態様に応じた課税方法を定めています。
そして、雑所得は、「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得」と定義されていますが、事業と業務との区別の基準は明確ではなく、業務の規定はありません。
最終的に「社会通念上事業として認められるかどうか」を総合的に判断することになると結論つけられますが、具体的には所得税基本通達35-2が基準となっているようです。
- その所得の収入金額が僅少と認められる場合
例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当する。
※「例年」とは、おおむね3年程度の期間を言う。
- その所得を得る活動に営利性が認められない場合
その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当する。
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいう。
- その所得に係る取引を帳簿に記録していない場合や記録していても保存していない場合には、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているとは認め難く、また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものと考える。
つまり、主たる収入があり、上記の基準を満たす場合は、事業ではなく、副業であると判断することで、損益通算を安易に認めない、それが、公平性を保つことになっていると考えられます。
【参考】
国税庁HP「法第35条((雑所得))関係」https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf