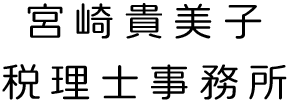青色申告を行う個人事業主が、生計を一にする配偶者やその他の親族で、専らその事業に従事する者に支払う給与を、必要経費として認める制度ですが、「専ら専従」しているかが税務調査で問題になる場合があります。
特に、法人の調査よりも所得税の調査では、事業と私生活の線引きが難しいところもあり、そもそも論を知っておくことが、判断基準となるのではないかと考えます。
【青色事業専従者給与の要件】
1.生計を一にする配偶者または親族であること。
2.その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること。
3.その年の6か月を超える期間、専らその事業に従事していること。年の途中で事業開始した場合などは、事業に従事可能な期間の2分の1を超える期間の従事があれば認められる。
4.支払う給与が労務の対価として相当であること
※このほか、青色事業専従者給与が税務上認められるためには、労務内容や勤務実態を明確に記録し、証拠として提示できる状態にしておくことが重要である。帳簿への記帳や振込決済を行い、支払い事実を明確にすることも求められる。
また、支払われる給与額が相当額を不相当に高額だと判断された場合、その課題相当額は経費として認められず、事業主から専従者への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性がある。
【判例紹介】
税理士業を営む被控訴人が、妻乙に支給した青色事業専従者給与を本件各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入して確定申告をしたところ、処分行政庁が、乙の労務の対価として相当であると認められる金額を超える部分の金額は必要経費に算入できないとして更正処分等をした事案(※1,※2)。
【法令解釈】
所得税法57条1項及び同法施行令164条1項は、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者と生計を一にする配偶者その他の親族で専らその居住者の営む事業に従事するもの(青色事業専従者)が当該事業から給与の支払を受けた場合に、「①その給与の金額でその労務に従事した期間、②労務の性質、③その提供の程度、④その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況、⑤その事業と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与の状況、⑥その事業の種類及び規模並びにその収益の状況」に照らしその労務の対価として相当であると認められるものは、その居住者のその給与の支給に係る年分の当該事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入する旨規定している。
【裁判所の判断】
・類似同業者給与比準方式及び使用人給与比準方式から検討したとおり、妻乙が支給を受けた本件各専従者給与は著しく高額であるから、不相当であることは明らかである。
・所得税法57条1項及びそれを受けた同法施行令164条1項は、親族に対する給与はとかく労務との対価性の有無を問わずに高額になりがちであって、無制限にこれを必要経費として認めると課税の適正公平を損なう危険性が高いことから、青色申告承認者に限り、かつ、提供された労務との対価関係が明確であるものに限り、必要経費として事業所得の金額の算定に際して控除することを認めたものであると解される。
【補足】
国税庁の使命に「内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現」が掲げられています。
「親族に対する給与は課税の適正公平を損なう危険性が高い」という考え方がベースにあるため、調査において支払いの実態や労務の実態、つまり労働時間や仕事内容がわかる日報などの証拠から調査し、相当な金額かを判断していくことになります。
当然、労働時間が短かったり、他に職業がある場合は、「専ら専従していない」と判断される場合があります。
また、労働の対価については、同じ仕事をしてもらった場合に他人に同じ金額を払うかどうかも1つの判断基準になるでしょう。
【参考】
※1 第一審・鳥取地裁平成24年6月22日判決 税務訴訟資料 第262号-125(順号11975)
※2 平成25年10月23日広島高裁判決 税務訴訟資料 第263号‐194(順号12318)
国税庁HP「青色事業専従者給与と事業専従者控除」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm)