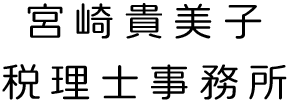法律の根拠がなければ、租税を賦課されたり、徴収されたりすることがないとする考え方を租税法律主義といいますが、これは憲法第84条で規定されているものです。
つまり、法律の根拠に基づいて納税の義務が生じる、言い換えれば、納税義務を成立させるために必要な法律要件が満たされなければ課税できないことになります。
そして、法律要件を満たしているかいないかは、「事実」によって判断することになります。
その「事実」を裏付けるものが「証拠」です。
令和元年5月30日東京地裁判決第269号-55(順号13278)では、どんな事実から、内縁の妻へ支払っていた給与が労働の対価でないと認定され、何をもって仮想隠蔽の事実があると判断されたかを検証していきます。
事実
1 内縁の妻を従業員(のちに取締役)として毎月45万円を給与手当として損金の額に算入していた。
2 内縁の妻の口座への振込金額は40万円。源泉所得税等の額及び社会保険料の額を差し引いた後の金額に、若干の加算をした金額を振り込んでいた。
3 内縁の妻の勤務時間は具体的に定められておらず、出退勤も管理されていなかった。日中は、日常の家事、仕事場の清掃を行う傍ら、代表者から指示された買い物(不祝儀袋、印紙、プリンターのインク、印刷用紙、中元・歳暮等の贈答品)、銀行における支払手続、振込用紙の取得、郵便局での郵便物の受発送、公共機関に提出する書類の用紙の取得や書類の提出などをしていたほか、代表者が所有する自動車の保険に係る手続を代わってすることもあった。また、代表者にかかってくる電話は代表者の携帯電話に転送される仕組みとなっていたため、代表者宛ての電話を内縁の妻が受けることはなかった。
これらの事実から、裁判所では、従業員としての労務の対価とは認められず、内助の功に報いる生活保障の趣旨で支給されたものと認めるのが相当あり、代表者に対して支給する給与に含まれるものというべきである、と判断しています。
そして、それは、役員給与の損金不算入を規定している法人税法第34条4項のその他の経済的な利益に該当するので、損金の額に算入していたことが認められないことになります。
次に、重加算税が賦課できるかということですが、重加算税を賦課できるかどうかの根拠条文は国税通則法第68条になります。
重加算税を課すには、以下の3つの課税要件が全て満たされている場合に限ります。
- 第65条第1項(過少申告加算税)の規定に該当する場合であるか
期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があつたときか
- 納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、
- その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき
つまり、どこに仮装、隠蔽があるか?ということなんです。
判例では、「代表者に対する役員給与であるにもかかわらず、内縁の妻に対する給与の支払であると出勤簿を作成するなどして、労務に従事していたかのように事実を装っていたことから、仮装して経理したものというほかない」と仮装の事実を認定しています。
今回は「出勤簿を作成していた」ことが直接証拠になっています。
出勤簿のような直接証拠、これがあれば事実が証明できるものがない場合は、その事実を推認できる間接証拠をかき集めて、点を線でつなぐような作業が必要になってきます。
例えば、税務調査では調査担当者から「質問応答記録書」の作成を求められることがあります。これも間接証拠になります。
決定的な証拠がない場合に、調査担当者はこの書面を作成し証拠としますが、裁判では証拠能力としては低いと教わりました。
個人的には、私は仮装隠蔽である直接証拠がなければ、重加算税は賦課できないと思っています。
なので、証拠能力が低い「質問応答記録書」の作成に協力する必要はないと思っているのです。
法律要件を満たしている「事実」があるかないか、それはどの証拠から証明できるか、それが税務調査です。
それが、わかって調査の立ち合いをするかどうかで、経営者の代理ができるのか、できないのかが決まってくるのだと思います。